

しかし、採用までは行けたとしてもなかなか継続となると難しいのよね
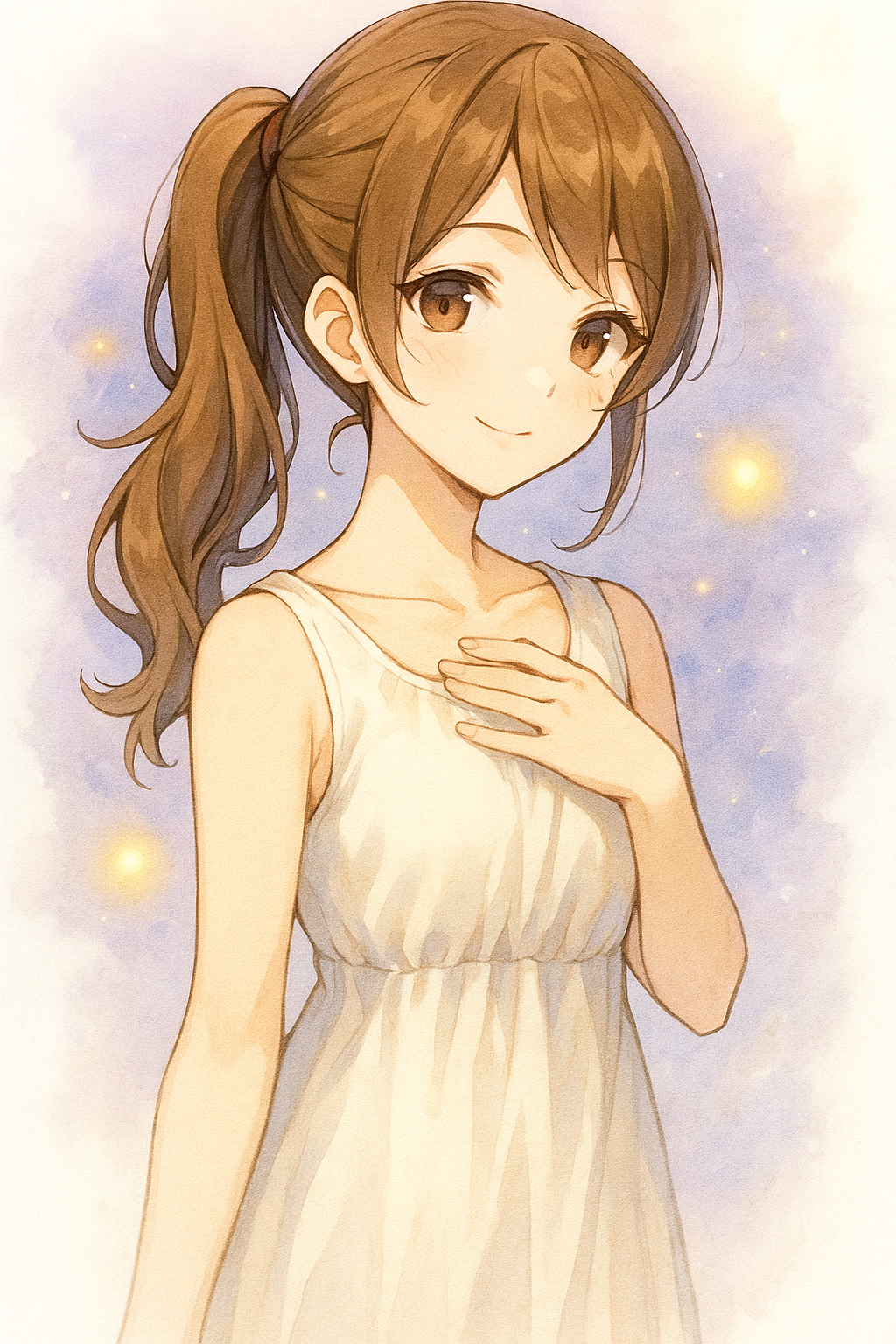
まあそうですよね、通院ですらキツイ場合もありますし、いきなり仕事して続けられるかと言われたら難しいです

ついつい、面接だと全力投球でいくけど、その後が難しいよね。
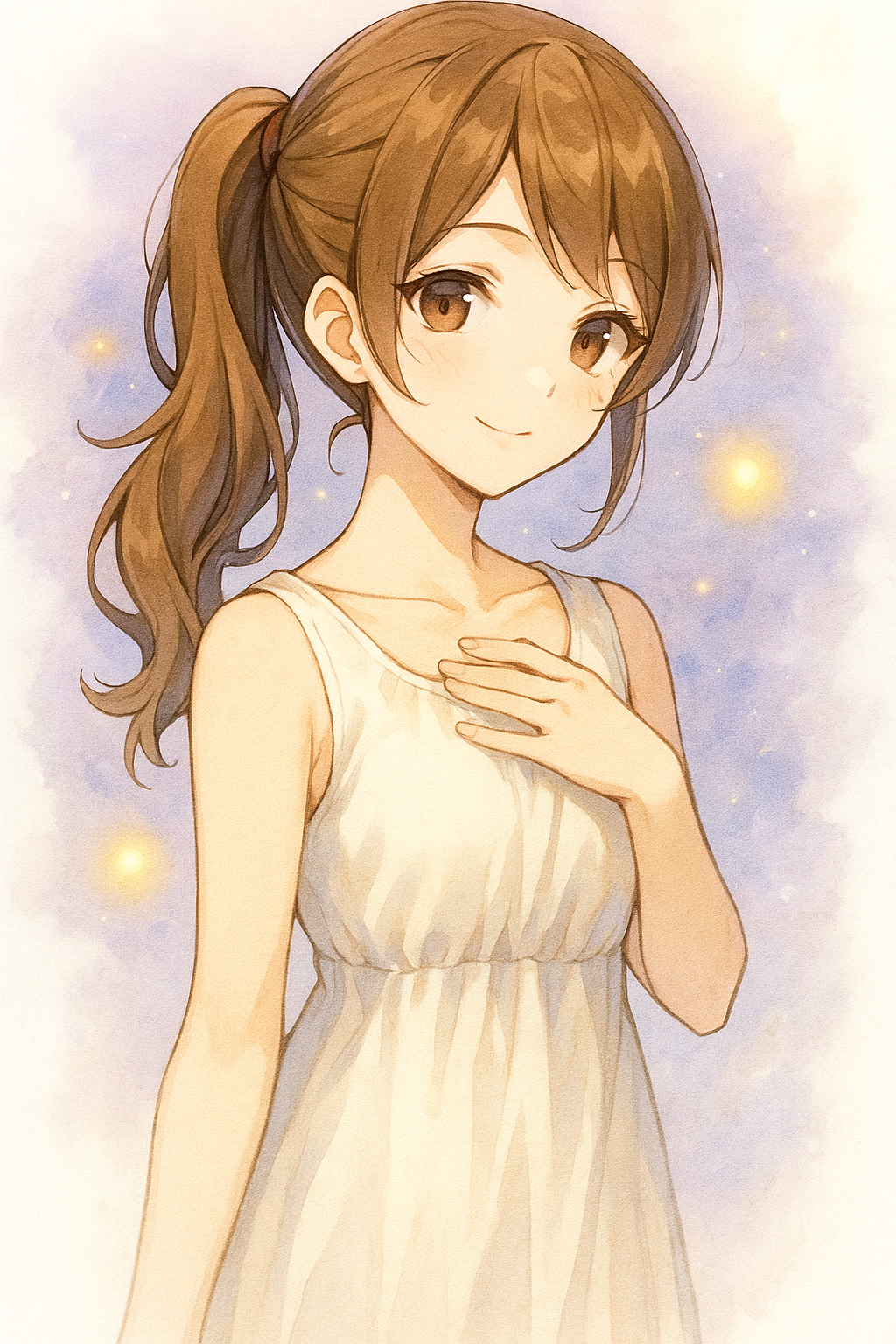
気持ちが切れたりしますしね

そうそう、特に双極性障害だと、ハイと鬱があるから面接後に燃え尽きみたいに鬱に切り替わったりするのよね
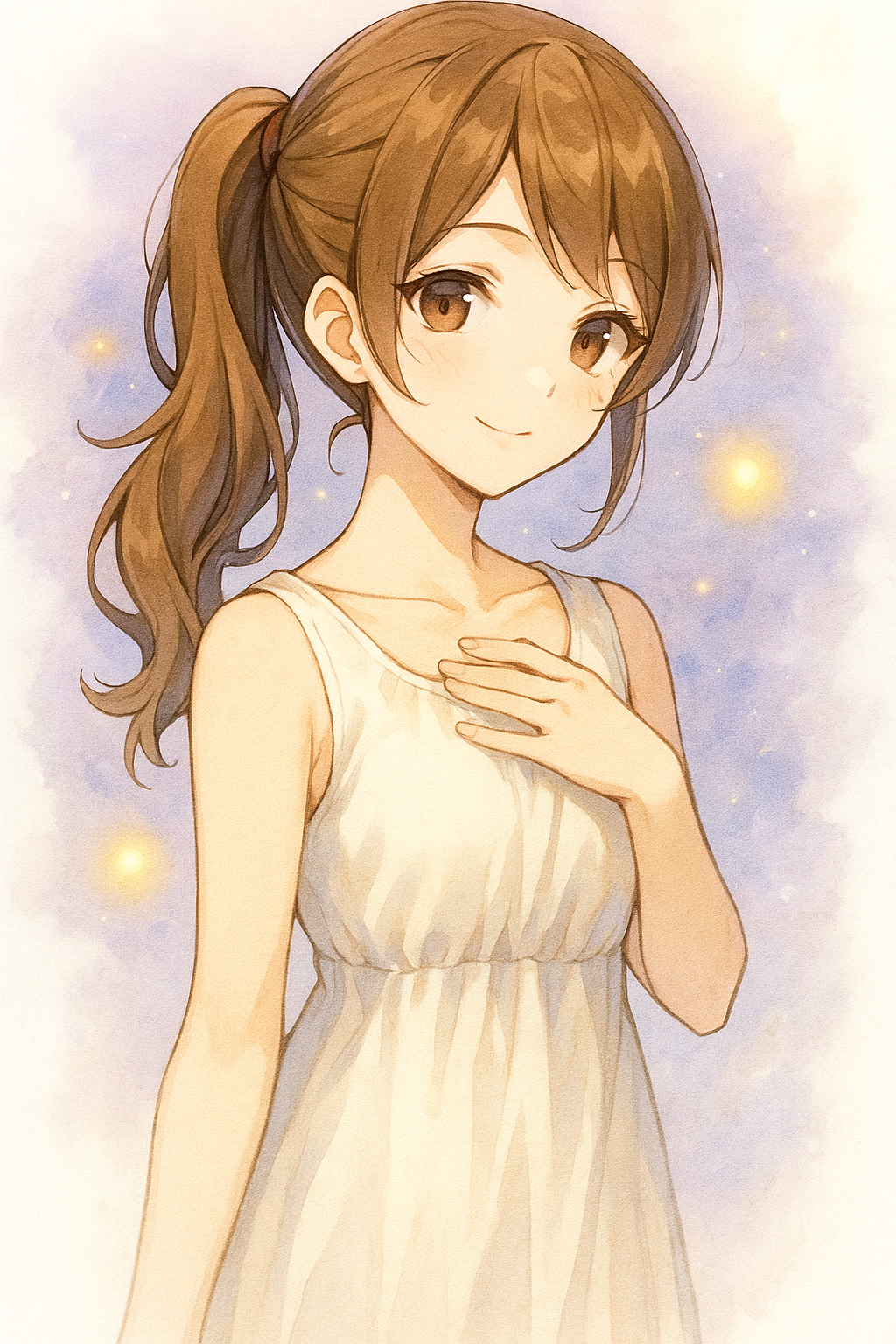
あー、私も経験あります。医師との問診では元気になって、家に帰って鬱になるみたいな

あるある、それに近いね!
注意点
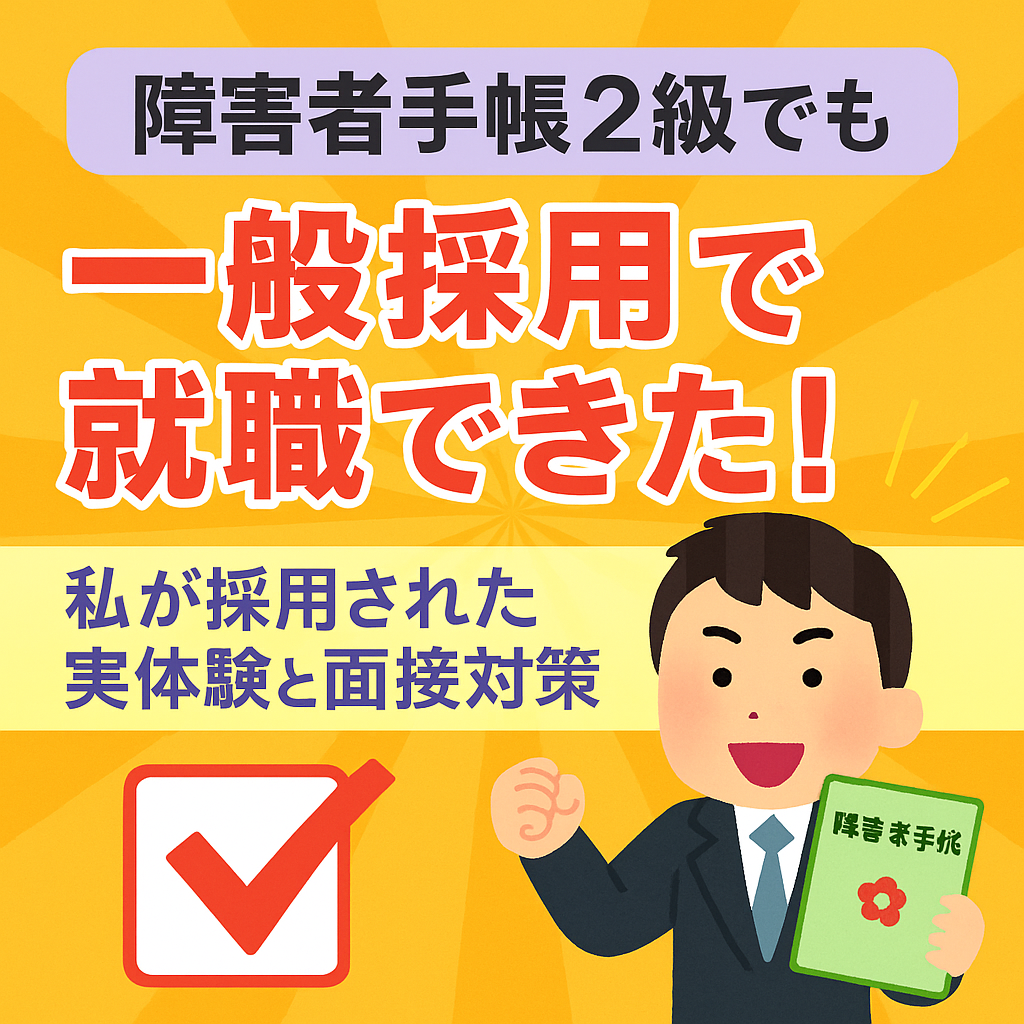
過去に、採用されるだけのノウハウ記事を書きましたが。
これ以上「不採用は嫌だ!とにかく採用をくれ!」という人や、面接のテクニックやヒントになればいいと思って書いた記事です。
ただリョウに言わせるなら、「採用がゴール」ではありません、我々障碍者はその先の定着が勝負なんです。
そのため、今回は就職後、継続するための必要な事を紹介します。
障害者雇用で「採用されたら終わり」じゃない!就職後に続けるために必要なこと
こんにちは、ファンキーガイ・リョウです。
55歳、発達障害と双極性障害を抱えながら、いくつもの転職を経て今も働いています。
今回は「障害者雇用=ゴール」だと勘違いしてしまいやすいテーマについて、ぶっちゃけトークとリアルな就労体験を交えて語っていきますね。
【はじめに】採用されたのに…うまくいかない現実
「やった!採用された!」「障害者雇用だから、もう安心でしょ?」
そう思ってた時期、私にもありました。でも実際は、
- 数ヶ月で辞めざるを得なかった
- 配慮されると思ったのに、現場では理解がなかった
- 自分の困りごとをうまく説明できなかった
- ペース配分を誤って退職と休養を余儀なくされた
こんな“あるある”が、障害者雇用の世界では日常茶飯事なんです。
採用はあくまでスタートライン。大切なのは、どうやって続けていくか? なんですよ。
第1章|なぜ「採用=ゴール」と思ってしまうのか?
障害者の就職支援では、どうしても“内定がゴール”のように扱われがちです。その背景には、
- 就労移行支援などの支援機関が「就職実績」を重視
- 求人情報が「障害者枠OK」ばかりで“就職後の姿”が見えない
- 本人も「働けるか不安」で“とりあえず入社”を目指しがち
という構造があります。
でも、実際に働き始めたら、
- 日々のストレスや疲労
- 人間関係や指示の受け取り方の難しさ
- 自分の特性に合わない業務内容
……こうした壁が立ちはだかります。
就職後に「想定外」が起きたとき、
どう対応するか?
誰に相談できるか?
配慮が得られる環境か?
こうした視点がないと、続けるのは難しくなるんです。
ちなみに【引用共同通信】
9000人以上の障碍者が解雇されているという。
こういうデータもあり、障碍者の定着がいかに難しいか、現実が分かるのではないでしょうか?
第2章|定着のために必要な3つの“準備”
1. 自分の特性・困りごと・強みを整理しておく
これは”自己分析”ってやつですね。私の場合、
- 注意の切り替えが苦手(発達障害)
- 気分の波で集中力が変動(双極性障害)
- ルーチンになれたころにイレギュラーが来ると体調を崩してしまう(発達障害)
でも、
- 人あたりはいいので第一印象がいい
- 接客が多く経験してきたので敬語や対応が得意
こうした“強み”と”困難”をセットで説明できるようにしています。
※ちなみにこうした強みや弱みの分析を手伝ってくれるが就労支援だったりします。
2. 配慮してほしい内容を具体的に伝えられるようにする
たとえば、
- 1日の業務予定を朝に確認できる
- イヤホンや耳栓の使用をOKしてもらう
- 感情的な叱責は避けてもらう
- 出社時間をラッシュ時間をさけてもらう
など、具体的な希望にしておくことが大事。
「何をされると困る」ではなく、「どうしてもらえると働きやすいか」で伝えるのがポイントです。
3. 支援者や相談相手を持っておく
働きながら悩みを抱えるのはよくあること。
- 就労移行支援のOBサポート
- 精神保健福祉士や産業カウンセラー
- 地域の障害者就労支援センター
- 相談室などの相談支援員・就労支援のスタッフさん
こうした機関を“働きながらでも使っていい”ことを忘れないでください。私は今も月1で就労支援の相談員から連絡がきて、状況を相談しています。
※就労支援の事業所によっては、就労後もフォーローをして企業との間に入ってくれるところもあり。
第3章|定着支援という制度をフル活用しよう
2018年からスタートした「就労定着支援」って制度、ご存知ですか?
これは、
- 障害者雇用で働いている方に
- 月1回のペースで
- 生活や就労の相談・アドバイスをしてくれる
という制度です。
対象は、
- 就労移行支援やA型B型から一般就労した人
- 障害者雇用で働いて6ヶ月以内の人
など、条件付きですが、うまく活用すればめちゃくちゃ心強いです。
発達や精神障害があると、どうしても近視眼的になりがちで、目の前のことでいっぱいいっぱいになり、相談できる相手がいるということを忘れやすくなります。
きついと思わなくても、綿密に連携や相談する習慣をつけて、いざというときに頼れるようにするのをお勧めします。
第4章|続けることが“未来の選択肢”を増やしてくれる
就職してすぐ辞めてしまった場合、「次に応募する会社」が不安になりますよね。
でも、半年、1年と続けられるようになると、
- 履歴書に堂々と「定着実績」を書ける
- 雇用保険などの制度利用にも強くなる
- 自分の働き方のパターンが分かってくる
など、“選べる”幅がぐっと広がるんです。
私も最初の職場では3ヶ月でダウン。でも、その経験があったからこそ、今の職場では1年以上続けられています。
【まとめ】就職はゴールじゃない、スタートだ
障害者雇用は、”採用”されるまでが大事にされがち。でも本当に大切なのは、
自分に合った環境で、無理なく働き続けること。
だから、次の一歩として、
✅ 自分の困りごとと希望配慮を紙にまとめてみる
✅ 定着支援や地域の相談窓口を探してみる
✅ 職場で「配慮されていないこと」があれば、具体的に相談してみる
就職したその先に、「働き続ける」という新たなストーリーを、一緒に描いていきましょう。
こちら過去記事ですが、実際にリョウが利用した支援機関があります。

支援機関単体だけでなく、相談支援員も併せて活用できると強い武器になりますよ。
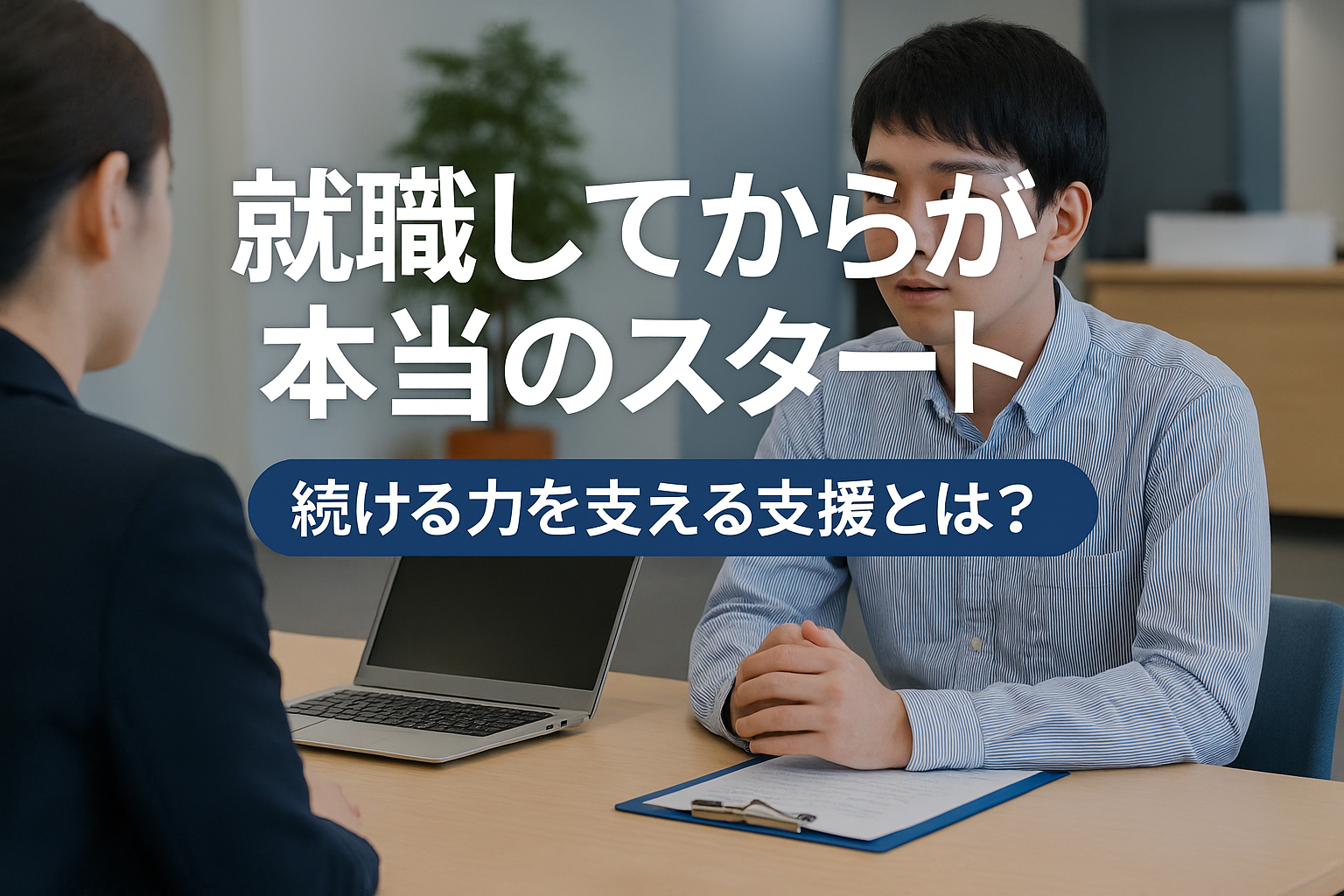


コメント