
※本記事はPRを含む場合がありますが、記載内容の中立性を心がけています。制度は変更されやすい領域のため、最終判断は公的窓口でご確認ください。

社会保険に入らないギリギリでシフトを調整してるって言ってた。
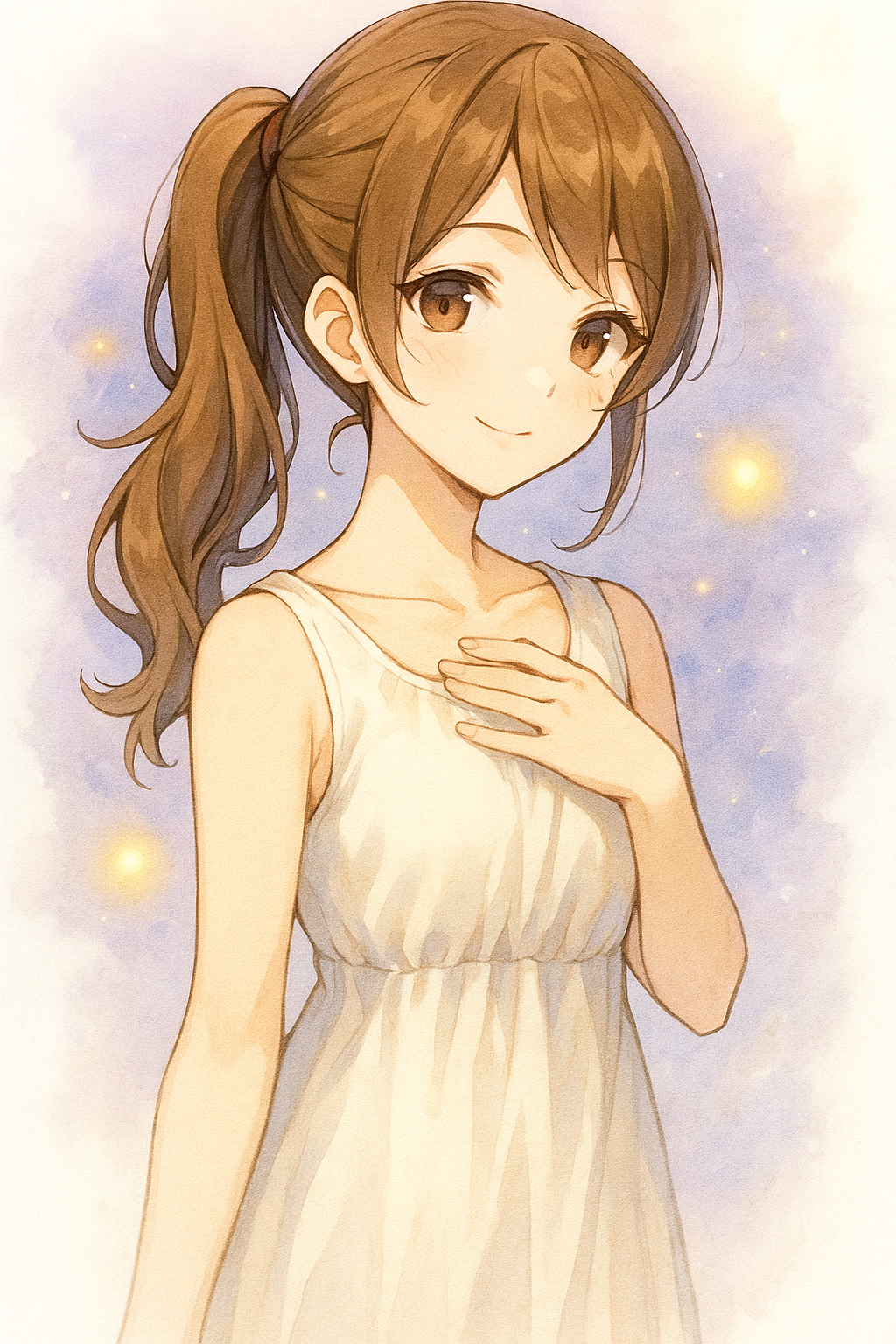

本人いわく、国民健康保険の方がケースによっては保険料が低いこともあるとか。
ただ、知的もあるらしいから正確には言えないし、ケースバイケースなのは間違いない世界だから一概には言えないよね。
障害年金2級×パートの“線引き”2025:週20h・月8.8万円・会社規模・106万/130万の壁までやさしく整理
最終更新:2025-08-25
「どこまで働くと社会保険に入るの?」「働いたら障害年金は止まるの?」——そんな不安を、2025年時点の制度でやさしく整理します。
週20時間・月8.8万円・雇用見込み・学生可否・会社規模という“加入ライン”と、加入のメリット/デメリット、106万円/130万円の壁の違い、65歳以降の受け取り方まで、要点だけをギュッとまとめます。
※制度は改正・運用変更が多い分野です。最終判断は年金事務所・健保組合・協会けんぽ・ハローワーク・税務署・社会保険労務士でご確認ください。
まずは30秒まとめ
- 短時間パートの社保ライン(健康保険+厚生年金):
週20h以上/月8.8万円以上/2か月超見込み/学生でない/事業所規模51人以上 → 原則加入(総合判断・任意除外は不可)。 - 障害年金と就労:支給の可否は「障害の状態」で判定。
就労=即停止ではないが、1〜5年ごとの診断書(障害状態確認届)で実態が確認される。 - 65歳以降:障害基礎年金+老齢厚生年金は併給可。障害基礎年金と老齢基礎年金は原則選択。
- 加入のトレードオフ:手取りは減るが、傷病手当金などの保障や将来の厚生年金が上乗せ。
- “壁”の超ざっくり:106万円=社保文脈、130万円=税・被扶養者文脈。意味が違うので混同注意。
1) “加入ライン”をやさしく図解(週20h・8.8万・51人要件)
判定に使う5つの観点(総合判断)
- 週の所定労働時間:20時間以上
- 賃金月額:月8.8万円以上(残業・賞与除外/月額判定)
- 雇用見込み:2か月超
- 学生でない(一部例外あり)
- 会社規模:常時51人以上(適用拡大の目安)
ポイント
・上記は総合で判断され、満たした場合に任意で外すことは不可(強制適用)。
・俗に言う“106万円の壁”は社保の目安(月8.8万円×12か月≒年106万円)。“130万円の壁”は税・被扶養者文脈で、物差しが異なります。
2) 「106万円の壁」と「130万円の壁」——何が違う?
- 106万円の壁(社保文脈):
月8.8万円以上・週20h以上・会社規模51人以上(目安)・学生でないなど、短時間労働者の被用者保険の適用に関わる話。
実務論点は社会保険料の天引きが始まること。 - 130万円の壁(税・被扶養者文脈):
税の配偶者控除/配偶者特別控除、健康保険の被扶養者認定など、別の基準が絡む。
⇒ “壁”は一枚板ではないため、社保・税・被扶養者で基準が違う前提で、それぞれ窓口確認が安全。
3) 交通費・複数就業・学生の“よくあるグレー”
- 交通費は賃金月額に入る?
非課税通勤手当の範囲や会社規定で取り扱いが分かれるため、就業規則/健保の案内/人事担当で必ず確認。 - 複数のバイトを“合算”する?
原則は事業所ごとの判定。ただし契約・実態により運用が異なる例あり。年金事務所/健保へ相談を。 - 学生は原則対象外だが例外あり
夜間・通信・定時制など、在学実態・就労実態で取り扱いが分かれることがあるため、在学証明等を持参し窓口確認。
4) 加入のメリット/デメリット(手取りvs保障)
加入する(被用者保険:健康保険+厚生年金)
- 手取りは減る(本人負担分の保険料が天引き)
- 傷病手当金/出産・育児関連給付など、現役向けの保障が使える
- 将来の老齢厚生年金(2階部分)が上乗せ
加入しない(=要件未達のまま:国保・国民年金)
- 目先の手取りは多めになりやすい
- 傷病手当金なし/厚生年金の上乗せなし(将来年金に差)
| 観点 | 加入する(被用者保険) | 要件未達(国保・国年) |
|---|---|---|
| 手取り | △(保険料天引き) | ○(増えやすい) |
| 保障 | ○(傷病手当金等あり) | △(原則なし) |
| 将来年金 | ○(厚年上乗せ) | △(上乗せなし) |
どちらが“得”かは人それぞれ。今の手取り重視か、万一の保障+老後重視かで逆転します。昇給・シフト変更・制度改正の節目で再計算を。
5) 障害年金2級と就労(誤解を解く3ポイント)
- 就労=即停止ではない:支給の可否は「障害の状態」で判定。
- 定期の診断書(障害状態確認届):1〜5年ごとに提出。日常生活・就労の実態が反映されやすい。
- 20歳前の障害基礎年金は所得制限あり。それ以外は原則として所得で増減させない(個別の例外や運用は窓口確認)。
実務のコツ
- 業務配慮(時間・休憩・負荷・担当変更など)を主治医に共有。診断書に反映されやすくなる。
- 無理な働き方を避ける(実態は診断書に反映)。
例:配慮がほぼ無いフルタイム勤務だと、その就労が可能な障害の程度と見なされ、障害年金の対象外となることがある。
障害者手帳を所持し、クローズで一般就労している場合は手帳等級の維持が難しくなる例も。 - 更新スケジュール管理:誕生月末が提出期限の目安。約3か月前に用紙が届くのが通例。
6) 65歳・70歳の“節目”をざっくり
- 65歳以降:
- 障害基礎年金+老齢厚生年金 → 併給可
- 障害基礎年金 と 老齢基礎年金 → どちらか選択(一人一年金の原則)
- どちらが有利かは人によるため、年金事務所で試算が最短
- 70歳:厚生年金の被保険者資格は喪失(=70歳以降は厚生年金保険料の徴収なし。健康保険は別扱い)。
7) 例でイメージ(3ケース+運用の分かれ目どころ)
- ケースA:週20h・月8.5万円・会社80人
月額が8.8万円未満 → 現行では加入対象外。昇給/シフト増で超えれば加入へ。 - ケースB:週19.5h・月9.0万円・会社200人
月額は満たすが週20h未満 → 要件不足で対象外。時間調整で一気に加入対象へ。 - ケースC:週22h・月8.6万円・会社60人
時間は満たすが月額未満 → 手当/昇給で8.8万到達なら加入に。
運用ノート:判定は所定労働時間+実態で見られがち。2か月連続で要件を満たす見込みなどがあれば切替の可能性。会社・年金事務所で確認を。
※親族経営など小規模事業所では、実務運用に幅が出る場合もあるため、公的窓口の見解を必ずもらうと安心。
8) 迷ったらこの順で!“加入フロー”テキスト版
- 会社規模:51人以上?(Yes/No)
- 週の所定労働:20h以上?
- 賃金月額:8.8万円以上?(残業・賞与除く)
- 雇用見込み:2か月超?
- 学生ではない?(例外は窓口確認)
→ Yesが続けば加入が原則。どこかでNoなら当面は要件未達。ただし昇給・時間増・就業実態の変化で切替の可能性あり。
9) よくある質問(FAQ強化版)
Q1. “扶養”と“社保の加入”は別物?
A. 別物です。社保(健康保険・厚生年金)加入判定と、税の配偶者控除/配偶者特別控除や健康保険の被扶養者認定は物差しが違うため、それぞれ確認が必要。
Q2. 交通費は月8.8万円の判定に含む?
A. 非課税通勤手当の範囲や会社規定により取り扱いが分かれます。就業規則・健保案内・人事担当で必ず確認を。
Q3. バイトを2つ掛け持ち。時間や賃金は合算?
A. 原則は各事業所ごとの判定。ただし契約・実態で運用が変わる例あり。年金事務所/健保へ相談が安全。
Q4. 学生は対象外と聞いたけれど、夜間/通信は?
A. 例外あり。在学実態・就労実態で取り扱いが分かれるため、在学証明等を持参して窓口確認を。
Q5. 障害年金は働くと止まる?
A. 就労=即停止ではありません。障害の状態で判断され、定期の診断書で実態確認があります。
業務上の配慮内容(勤務時間・休憩・担当業務など)は主治医と共有し、診断書に反映してもらいましょう。共有が不足すると、障害年金が停止・等級が下がる等のトラブルにつながることがあります。
Q6. 雇用保険はどうなる?
A. 目安は週20h以上+31日以上の雇用見込み(失業等給付に関わる)。社会保険(健保・厚年)とは別枠で確認。
10) 今日のチェックリスト(保存推奨)
- 〔会社規模〕51人以上か
- 〔所定労働〕週20h以上か
- 〔月額〕8.8万円以上か(当面の目安)
- 〔学生か否か〕例外に当たらないか
- 〔診断書更新〕誕生月末提出/3か月前から準備
- 〔家計判断〕加入の有無で手取り・保障・将来年金がどう変わるかを簡易試算
- 〔扶養/税〕配偶者控除・被扶養者認定も別途確認
- 〔生活保護との併用〕要件や控除が異なるため、自治体窓口で別途確認(当サイトでは別記事で解説予定)
障害者雇用やパート探しは、専門エージェント/就労移行支援の活用も一案
障害者向け転職エージェントや就労移行支援では、「どの程度働くと線引きに触れるか」「どのような配慮を伝えると通りやすいか」など、実務的なヒントを得られることがあります(公的基準は日本年金機構・年金事務所等で必ず確認)。
なお、一般的な転職エージェントはフルタイム志向が中心のことも多いので、短時間パート前提ならA・B型へ移行もできる就労移行支援や地域の就業支援窓口も併用が現実的です。

リョウの経験的に、身内で経営しているような昔ながらの少数企業のパートで、年寄りを多く雇用してるようなところは、働き方の融通が利きやすいことも多い。
下手に理解の薄い障害者雇用よりはやりやすかったと個人的には思ってます。
関連記事:就労移行支援で働き方のヒントを得る(A・B型含む)
免責・確認先
本記事は2025年時点の一般情報です。個別条件(被保険歴・雇用契約・配偶者の加入・地域差 等)で結論は変わります。
年金事務所/協会けんぽ・健保組合/ハローワーク/税務署/社会保険労務士などの公的・専門窓口で必ずご確認ください。
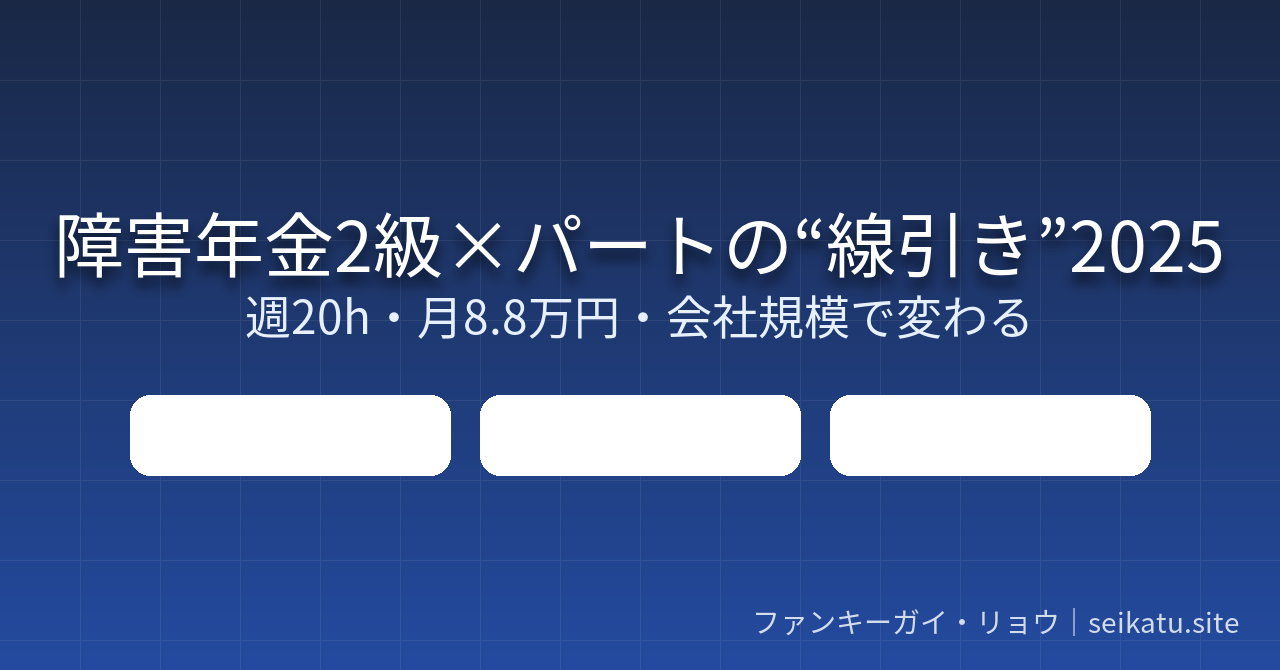
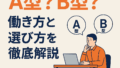
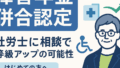
コメント