
※この記事はPRがあります。
お金がない障害者の就労移行|費用ゼロで通う方法
※本記事は制度の一般的な概要です(2025年9月時点)。最終判断はお住まいの自治体の福祉窓口・ケースワーカーに確認してください。
導入:お金がなくても「通える道」はあります
「就労移行支援に興味はあるけど、お金がない……」——これ、よく届く相談です。
結論から言うと、生活保護や住民税非課税世帯の多くは自己負担が“0円”で利用できます。
自己負担が発生する場合でも月額上限が決まっており、青天井にはなりません。まずは制度の“基本”を押さえましょう。(厚生労働省)
1|就労移行支援の費用の基本(ここが最重要)
就労移行支援の自己負担は原則1割ですが、所得に応じた「負担上限月額」が設定されています。代表的には次の4区分です(いずれも月額の上限)。
- 生活保護世帯:0円
- 住民税非課税世帯(低所得):0円
- 一般1(課税・所得割16万円未満):9,300円
- 一般2(上記以外):37,200円
※「世帯」の範囲は18歳以上は本人と配偶者が基本。詳細は厚労省資料を必ず確認。(厚生労働省)
目安として、就労移行支援の1割自己負担は日額数百円程度(加算により増減)。ただし月額上限があるため、実際の負担は上限内に収まります。(リハビリテーション情報センター)
2|0円で通う条件と、必要な手続き
2-1. 0円になりやすいケース
- 生活保護を受給中:上限月額は0円。
- 住民税非課税世帯:上限月額は0円。
(例示の条件や判定は自治体の認定に依存)(厚生労働省)
2-2. 申請〜利用開始までの流れ(カンタン版)
- 市区町村の障害福祉課へ「就労移行支援を利用したい」と相談
- 必要書類の提出・認定調査
- サービス等利用計画の作成(相談支援専門員と)
- 障害福祉サービス受給者証が交付
- 事業所と契約・通所開始
(「受給者証」が鍵。自治体窓口が起点です)(WAM)
2-3. 「上限額管理」でムダ払いを防ぐ
複数サービスを併用する場合は「上限額管理」を設定し、月上限超の自己負担が発生しないよう調整します(受給者証の欄に管理事業所名が記載)。
申請や指定方法は自治体・事業所で案内してくれます。(厚生労働省)
3|見落としがちな交通費・昼食代と、その対策
- 交通費:自治体によって通所交通費助成がある場合があります(支給条件・上限は市区町村ごとに異なる)。まずはお住まいの自治体名+「就労移行 交通費」で検索→窓口で確認。(一般社団法人 就労支援センター)
- 昼食代:事業所で提供がある場合は実費がかかることも。自治体で補助が設けられる場合もあるため、合わせて確認を。(神戸市公式サイト)
補足:利用料の1割負担とは別に、こうした実費は発生し得ます。事前に「交通費」「昼食」の有無・金額を事業所に確認しましょう。(WAM)
4|利用期間は原則2年。延長・再利用の考え方
- 就労移行支援の標準利用期間は2年。状況に応じて最大3年までの支給決定が可能、再利用(複数回利用)も個別判断で認められます。(厚生労働省)
- 就職後は就労定着支援で最長3年6か月、職場定着をサポートする仕組みがあります。(厚生労働省)
ポイント:「2年の中で就職までの道筋を作る」が基本設計。延長や再利用は必要性の根拠(体調・能力変化、実習・内定待ち等)を整えて、自治体と相談しましょう。(厚生労働省)
5|生活保護・障害年金との関係/アルバイト併用の注意
- 収入申告:生活保護や各種給付と就労収入の関係は個別性が高いため、福祉事務所のケースワーカーへ必ず事前相談を。
- アルバイト併用:自治体の運用が分かれます。例として札幌市は、就労移行利用者の短期アルバイトを原則不可と明確化(対象者像に合致しないため)。お住まいの自治体ルールを必ず確認してください。
6|ケーススタディ:生活保護・所持金わずかでもスタートできた例
Aさん(40代・精神障害・生活保護)
- 所持金がほぼゼロで交通費が不安 → 区役所で通所交通費助成を確認し、適用見込みに。
- 利用料は上限0円。昼食は自作弁当+事業所のフリードリンク。
- 3か月は午前のみ通所→体力回復→PC訓練と職業準備性→実習→内定。
- 就職後は就労定着支援で勤務調整・通院配慮をフォロー。(厚生労働省)
7|よくある疑問Q&A(サクッと解消)
Q1. 手元に現金がなくても申請できますか?
A. 可能です。まずは福祉窓口で受給者証の相談・申請へ。生活保護・非課税なら0円になることが多いです。(厚生労働省)
Q2. 交通費が心配です。
A. 自治体の助成・事業所の送迎・通所頻度の段階調整など選択肢があります。窓口と事業所の両方に確認を。(一般社団法人 就労支援センター)
Q3. 2年で就職できなかったら?
A. 延長・再利用は個別判断で可能性があります。体調や能力の変化根拠を整え、相談を。(厚生労働省)
Q4. 就職後のサポートは?
A. 就労定着支援で最大3年6か月、勤務・人間関係・体調面をフォローできます。(厚生労働省)
8|今日から動くための3ステップ(テンプレつき)
Step1:自治体に電話(障害福祉課)
- フレーズ例:「就労移行支援を利用したいので、受給者証の申請手続きと負担上限月額、通所交通費助成について教えてください。」
Step2:事業所の見学・体験を予約
- 見学はたいてい無料。持病・服薬・通所ペースの不安も伝えましょう(午前のみ等の段階通所が可能か確認)。
- 経済的な問題なども伝えると、実際の自己負担額の目安や抑える方法を教えてくれることもあります。
障がいのある方への就労移行支援【パーソルチャレンジ・ミラトレ】
![]() 問い合わせで相談するのも手ですし、実際に説明会や体験会で聞くのも手です。事業所によっては受給者証の取り方も手伝ってくれることもあります。
問い合わせで相談するのも手ですし、実際に説明会や体験会で聞くのも手です。事業所によっては受給者証の取り方も手伝ってくれることもあります。
Step3:ハローワーク障害者専門窓口と地域障害者職業センターに相談
- 仕事情報、面接同行、職業評価・ジョブコーチなど就職直結の支援が受けられます。(ハローワーク)
まとめ:お金がないは、スタートを止める理由にならない
- 生活保護・非課税世帯は自己負担0円が基本。その他でも月上限あり。(厚生労働省)
- 交通費・昼食などの実費は自治体助成や事業所の仕組みで軽減できる可能性。(一般社団法人 就労支援センター)
- 期間は原則2年。必要なら延長・再利用も個別に検討。就職後は定着支援で伴走。(厚生労働省)
次の一歩:今このあと、あなたの自治体の障害福祉課に一本電話。受給者証・上限月額・交通費助成の3点を確認→見学予約→ハローワーク窓口へ。ここまで動ければ、道は開けます。(ハローワーク)
参考リンク(公式・公的)
- 厚生労働省|障害者の利用者負担(上限月額の区分)(生活保護・非課税は0円、一般1は9,300円、一般2は37,200円)(厚生労働省)
- 厚生労働省|就労定着支援の実施(最長3年6か月) (厚生労働省)
- 厚生労働省|ハローワーク(障害のある方向けサービス) (ハローワーク)
- JEED|地域障害者職業センター(全国窓口) (ジード)
- 札幌市|就労系サービス手引き Q&A(バイト併用の扱い等)

まあ俺の場合は、もう生活保護を受けているから負担金なかったけど。作業所と違って賃金はでないから、その点は注意だな。
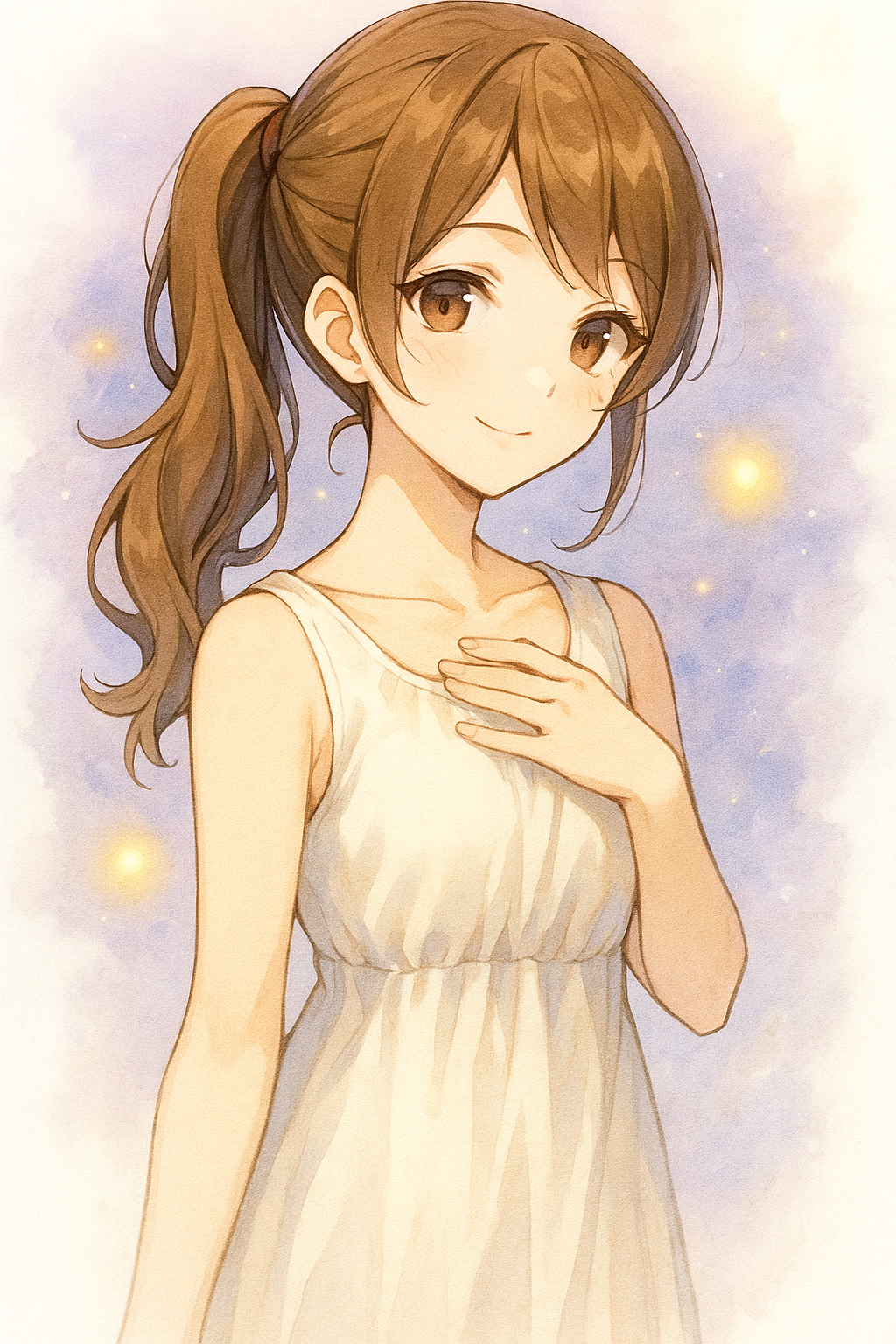
生活がガラリと変わって急な出費に戸惑うケースもあるらしいですしね

まあ、近年は発達とかの問題もあるから……このあたりは個人差と障害特性的にどうしても出てくる問題ではあるな
スタッフや可能なら相談支援室の相談支援員などの知恵をかりて、乗り越えていきたいね
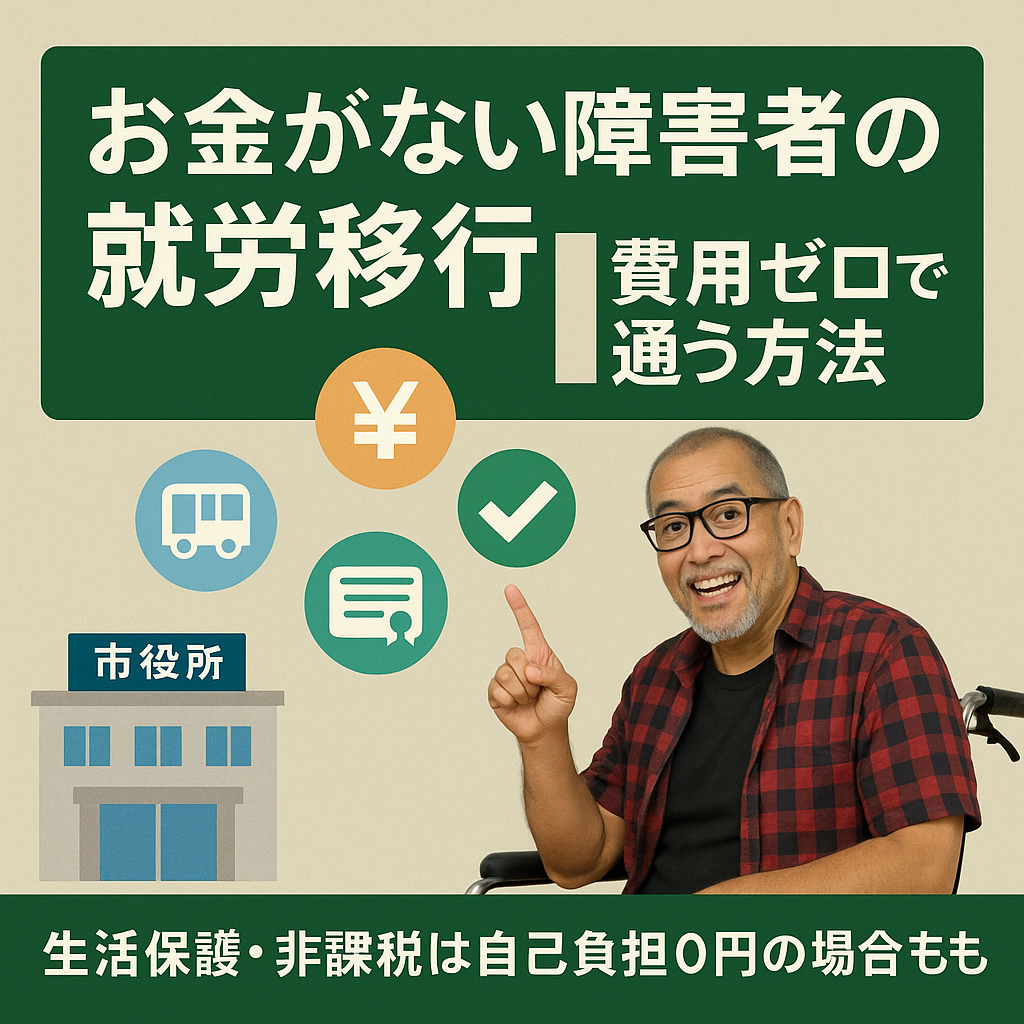


コメント