
※この記事はPRがあります。
就労移行支援体験談|二十代男性Yさんの“その後”
――辞めなくていい。助けを呼ぶ順番さえ、間に合えば。
0. プロローグ:あの日の「ため息」をぼくは忘れない
長めのプログラムで体験談を話し続けた、Yさんの話は入社したところで終わらない。
言いにくそうに、そして向き合う科のように彼はつづけました。
「ここからは、入社してから私がミスをして潰れかけた話です」
この言葉で一部の利用者が顔色を変えた。
後になって感想をグループで話すとき、どうやら入社が目的となっていたらしい。リョウもこの話をきいて、分かっていたつもりだったが入社がゴールではないと改めて思い知らされました。
1. あらすじ(前回のおさらい、30秒)
就労移行の特別プログラムを経て、Yくんは事務系職に内定。
まじめ、根っこが粘り強い。でも注意の配分が難しく、初見手順で取りこぼしやすい――そんな特性がある。
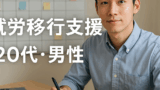
詳しくはこちらの前回記事を参照ください。こちらを読んでからこの記事を見ていただいたほうが、色々とイメージしやすくなるのでお勧めです。
それでも、彼はコツコツと努力を重ねて、受け入れてくれる会社に巡り合えた。
今回はその後に起きた話です。
――つまずきの正体は「静かに」「見えないうちに」
最初のミスは、小さな入力欄の取り違えだった。
「多分、ここからだろう」と見切りで修正、正確な数字や箇所をきちんとあっていたかどうか気づくのは、いつも遅れてからです。
いつもより多いダンボールを眺めて、誰にも言えないまま、Yくんは自分ひとりで背負った。
残業で遅くなり、家でも深夜まで責任問題などのケースを検索。布団に入っても目は冴える。
薬は“調子がいいから”と自己判断で抜いた。一度辞めた習慣は再開して定着させるには支援が必要な人もいます。それが限界の状況の下では思い出せないものです。
睡眠はほどけ、生活リズムは音もなく崩れていく。
母親が変化に気づいたのは、生気のない顔をしながら食事をして。麦茶のコップを落とした夜だったという。
その瞬間、物語は動く。
母親は、父親と話しながら子供の身を案じつつ。
「そういえば」と就労移行で受け取っていた定着支援の連絡先を思い出す。
ここで担当者だったスタッフさんにつながり、現状と客観的な第三者の見た様子が伝わりました。
――「辞めないで続ける」を現場で実装
支援員は、まず生活の土台を確認した。睡眠、食事、服薬。それから、脳の“疲れ”がどこで増えるかを聞く。
会話の端から浮かび上がったのは、一つの事実。可視化してくれていた上司が転勤していた。
気を許せる人がいなくなった穴は、体調より先に集中を連れていく。
また生活の状態からスタッフは主治医に繋ぎました。
結果はシンプル――睡眠障害の一歩手前。
服薬の内容を調整して、タイミングを戻し生活リズムを取り戻すためのステップに入ります。
職場には、本人同意をとって要点だけ伝えた。
お願いしたのは派手な制度じゃない。送信前の“5分ダブルチェック”と、画面に貼る小さな手順メモ。
またダブルチェックしやすいよう、先輩や配慮のうまい人がついてくれたのがYさんの状況にはプラスに働いたようです。
退職も、休職も、要らなかった。
周りのサポートが間に合った、すべてがうまくかみ合った事例でした。

このように周りが気付いて支援が間に合うケースはなかなか、難しいものがあるらしく。本人も「首になるのでは??」という思いから。
素直に悩みや手こずってることを言えない事も多いそうです。
――このケースが教えてくれたこと(3点だけ)
- 人の弱さじゃなく、順番の問題:自己解決→夜の検索→孤立の順を、相談→医療→職場の小改修にひっくり返す。
- 仕組みに寄りかかる:ダブルチェック・手順付箋・送信前5分。道具を活用すると、余裕が生まれる。結果として、それが心の回復につながります。
- 同意と範囲:共有は本人同意で。巻き込みは最小限、でも速さは最大に。
家族へ――あなたの“声かけ”が最初の救急箱だ
「辞めるか続けるか」を迫られる前に、“相談の順番”を一緒に作る。
怒られる前に止める方法を、本人より先に“言葉”にしてあげる。
“手助け”じゃない。“設計図”を肩代わりするだけだ。
Yくんの母親がやったのは、たった一回の電話。
でも、その一回が、彼の未来を今日へつなぎ直した。
現場のミニ実装(小さく、すぐ、効果が出る)
- ダブルチェックはしっかりしてもらう。
- ブラウザのブックマーク名を【受注】【発注】のように“でかい言葉”にする。
エピローグ:特別プログラムのOB訪問総括
Yさんの様子は見た目は普通の人と変わりません。
ですが、話す内容は我々のような注意多動や発達を持つ人と変わらない内容でした。
そして、誰にでも起こりうるミスについて。どのタイミングでリカバリーをしてもらうか?周りの助けをどう使うべきか?考えさせられるものでした。

大事なのは自己判断せず。周りの助けをきちんと求めて、活用できる事です。Yさんは実家暮らしだったからご両親という助けがありました。
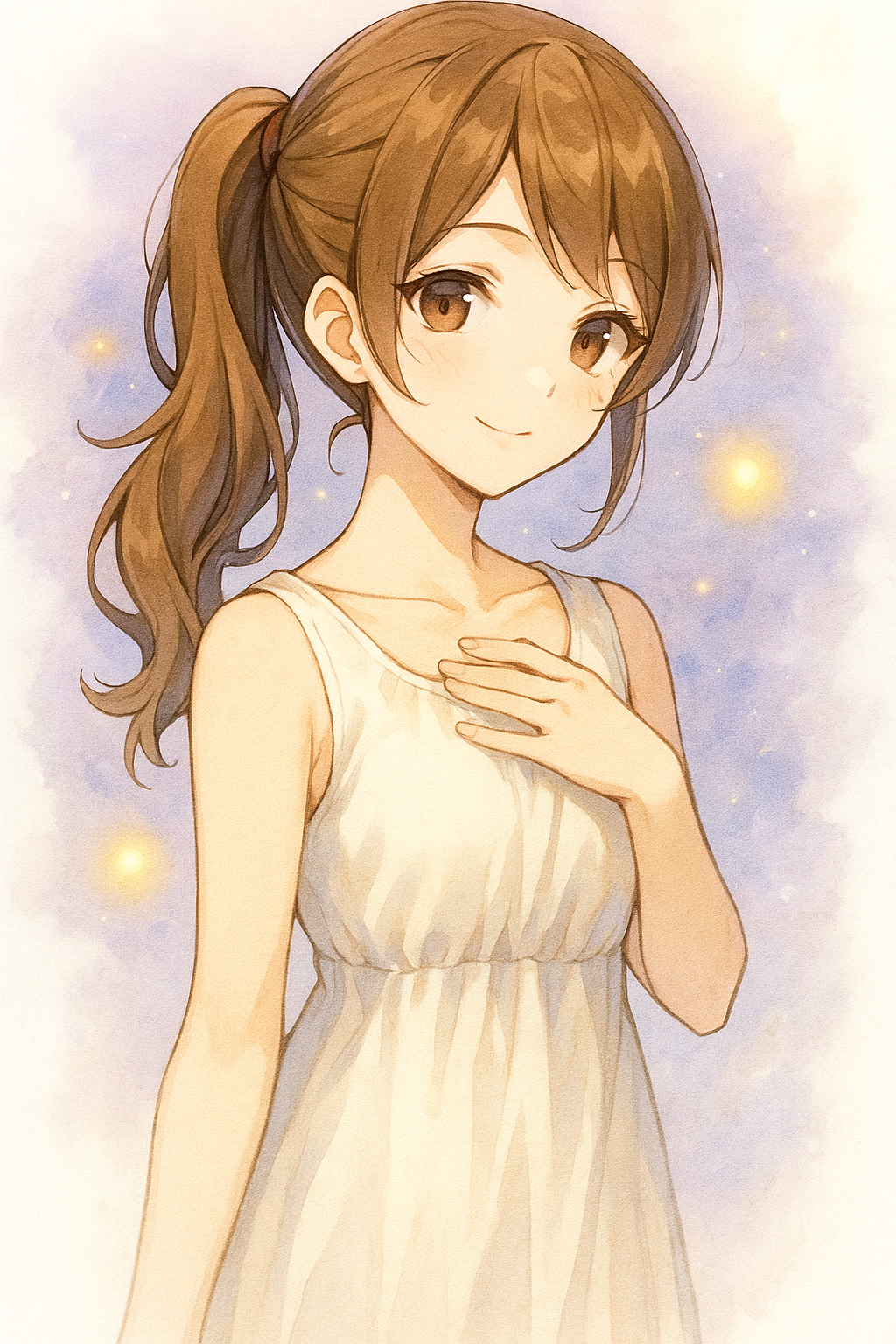
私達みたいな単身者だと、見ていてくれる人はいないので自分で気づいて行動しないといけませんね……。
まとめ(行動の一歩)
- 連絡リストを紙で可視化:支援員/主治医/上長
- 3行メモを今日から記入
これは“辞めないで続ける”ための現場知。
あなたの明日が、今日より一歩だけ軽くなりますように。
就労移行支援を賢くつかい、相談や分析などきちんと傾向と対策を作りたい人はこちらからご相談が可能です!
障がいのある方への就労移行支援【パーソルチャレンジ・ミラトレ】
![]()
難病で障害者年金を受けているけど、障害者手帳の対象外ですって方も通えることがあります。スタッフさんに相談してみましょう!
※本記事は体験と一般情報に基づくもので、医療・法律の助言ではありません。治療・就業の判断は主治医・所属先の規程に従ってください。

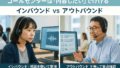

コメント